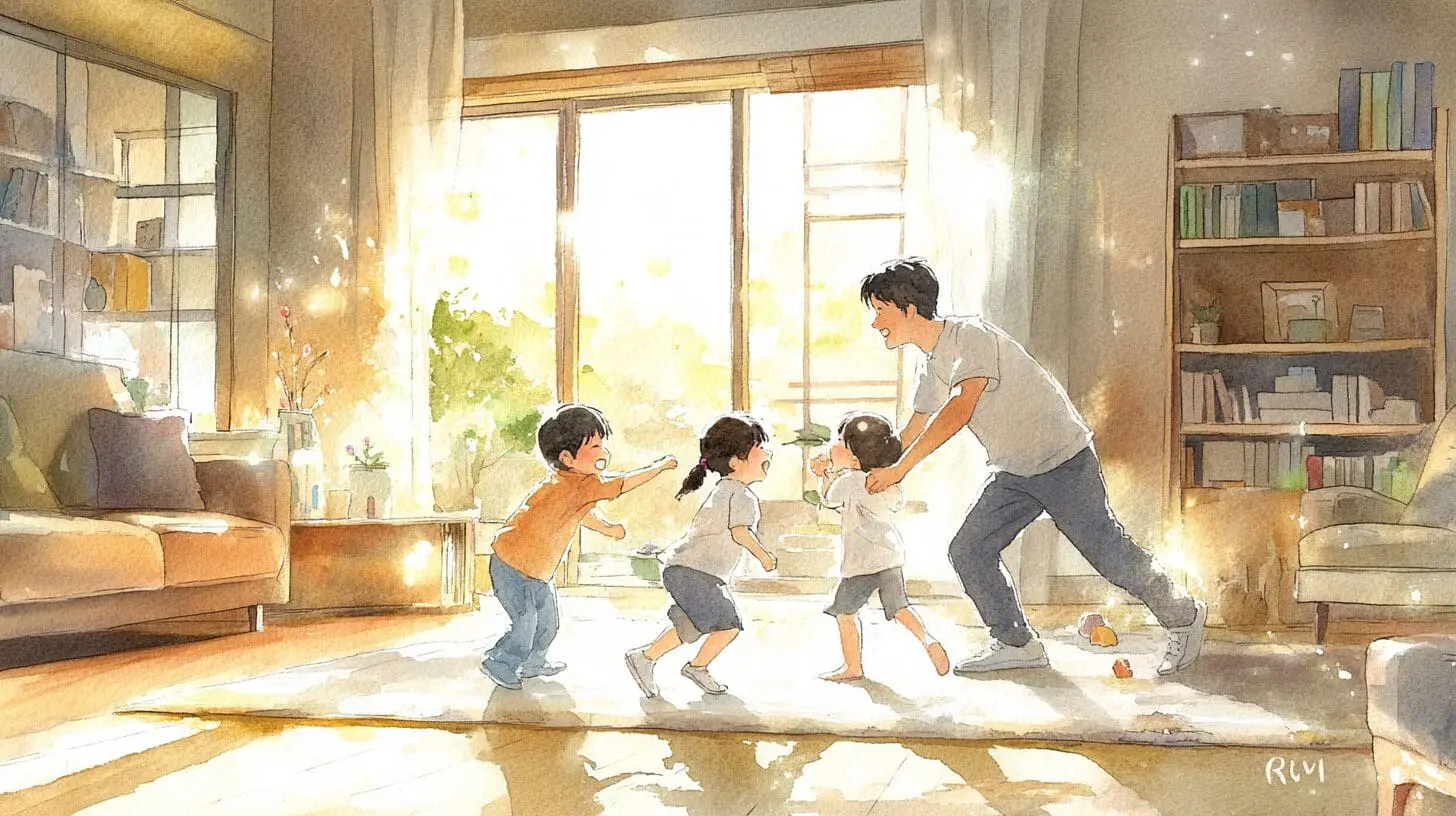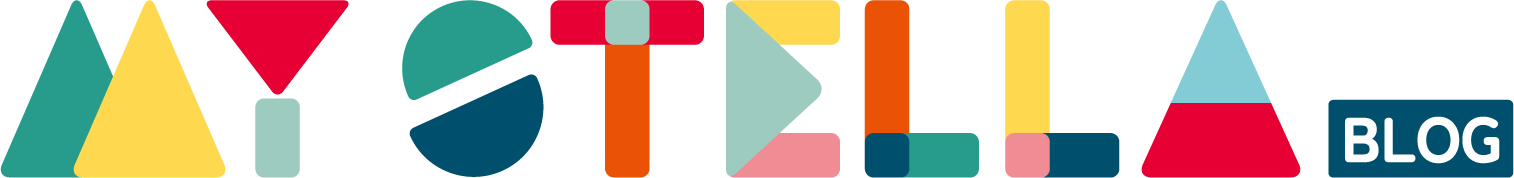子どもたちが夢中になる「忍者」の世界。
変身や隠れ身の術、手裏剣など、その魅力は尽きませんよね。実は、子どもが忍者に惹かれるのには深い理由があったのです。この記事では、なぜ子どもたちが忍者に夢中になるのか、その心理的背景と発達段階との関係を紐解いていきます。
忍者好きは単なる「かっこいいから」だけではなく、子どもの自立心や問題解決能力の発達と密接に関わっていること、さらに「なりきり遊び」を通して得られる成長の機会についても解説。
お子さんの忍者ブームに困惑しているパパママも、この記事を読めば「忍者好き」を応援したくなるはず。子どもの成長を後押しする忍者の魅力、一緒に探っていきましょう!
忍者の魅力①「変身できる」から!
子どもたちが忍者に夢中になる理由の一つ目は、何といっても「変身」の要素です。普段は一般の農民や町人に姿を隠し、任務のときだけ忍者に変身する…というこのギャップが、子どもたちの心をつかんで離しません。
「忍者=変身ヒーロー説」!戦隊ものやヒーローと共通する要素
よく考えてみると、忍者は日本古来の「変身ヒーロー」といえるのではないでしょうか。昼間は普通の人、しかし必要なときには特別な装束に身を包み、超人的な能力を発揮する—これは現代の戦隊ヒーローやスーパーマンなどと共通しています。
忍者と現代ヒーローの共通点として、「変身」「秘密の正体」「特殊能力」「使命感」が挙げられます。子どもたちは自分も同じように「特別な存在になれる」という願望を、忍者ごっこを通して実現しているのです。
| 忍者の特徴 | 現代ヒーローとの共通点 | 子どもへの影響 |
|---|---|---|
| 変身(普段の姿→忍者装束) | 戦隊ヒーローやスーパーマンの変身 | 自分も変われるという希望 |
| 秘密の正体 | ヒーローの秘密のアイデンティティ | 秘密を持つワクワク感 |
| 特殊能力(忍術) | ヒーローの特殊能力 | 可能性への憧れ |
「なりきり遊び」が子どもの成長に大事な理由とは?
忍者にはなれなくても、忍者に「なりきる」ことはできます。この「なりきり遊び」は子どもの発達において非常に重要な役割を果たしています。

発達心理学の研究によると、なりきり遊びには次のような効果があります:
- 想像力と創造性の発達
- 社会性や協調性の向上
- 感情コントロールの学習
- 問題解決能力の育成
- 言語能力の向上
「なりきり遊び」を通じて、子どもたちは自分とは異なる視点や価値観を体験し、共感する力を育んでいます。忍者になりきることで、「静かに動く」「周囲をよく観察する」「困難を乗り越える」などの体験ができるのです。
忍者になりきる遊びのバリエーション
子どもたちの忍者なりきり遊びには様々なパターンがあります:
- 手ぬぐいや黒い服で忍者装束を作る
- 折り紙で手裏剣を作って投げる練習をする
- 家の中や公園で「忍び歩き」の練習をする
- 友達と忍者チームを組んで秘密の作戦を立てる
- 障害物をくぐり抜けて忍者修行ごっこをする
こうしたなりきり遊びは、幼児から小学生まで多くの子どもたちにも大人気です。特に折り紙で作る手裏剣は、指先の器用さも育てる教育効果の高いあそびです。

忍者の魅力②「すごい技がある!」
忍者といえば、誰もが思い浮かべるのが「忍術」や「忍者道具」ではないでしょうか。子どもたちが忍者に夢中になる最大の理由の一つは、この「すごい技」の数々です。子どもたちは「できないことができる」という非日常的な体験に強く惹かれるのです。
手裏剣・分身の術・隠れ身の術…「ありえないことができる」がワクワクを生む!
子どもたちが忍者に憧れる最大の理由の一つが、現実世界では決してできない「特別な技」を持っているということです。手裏剣を投げる、分身の術で自分のコピーを作る、煙に包まれて姿を消す…これらは日常では体験できないからこそ、子どもたちの想像力を刺激します。
国立歴史民俗博物館の調査によると、忍者が使用したとされる道具は80種類以上あるとされています。子どもたちは多彩な忍者道具に魅了され、その一つ一つに物語を見出します。実際に伊賀流忍者博物館などでは、本物の忍者道具を見ることができ、子ども連れの家族に人気のスポットとなっています。
| 忍者の技・道具 | 子どもが魅力に感じるポイント | 実際の歴史的背景 |
|---|---|---|
| 手裏剣 | 遠くの的に当てる爽快感 | 実際は主に相手の注意をそらすための道具 |
| 分身の術 | 自分が複数人になる不思議さ | 藁人形や人形を使った錯覚技術 |
| 隠れ身の術 | 姿を消せる特別感 | 周囲の環境に溶け込む擬態の技術 |
| 水蜘蛛 | 水の上を歩ける不思議さ | 水面を移動するための簡易的な装置 |
「MY STELLA(マイステラ)」の読者アンケートによると、5〜8歳の子どもたちの約70%が「手裏剣投げ」を「やってみたい忍者の技」の1位に挙げています。また、多くの子どもたちが家庭で新聞紙や折り紙で手裏剣を作って遊んだ経験があるそうです。
忍者の技は、子どもたちの「もしもこんなことができたら」という空想の世界を広げてくれる格好の素材なのです。
「動きがかっこいい!」子どもはダイナミックなアクションに夢中
忍者の動きは、跳ねる、飛ぶ、回転する、壁を走るなど、非常にダイナミックです。幼児期から小学校低学年の子どもたちは体を動かすことが大好きで、忍者の動きはまさに彼らの憧れそのものです。
例えば、以下のような動きが子どもたちに人気です:
- 忍者走り(かがんで素早く移動する)
- 壁のぼり(マットを使って壁のぼりの真似をする)
- 忍者バランス(細い線の上を落ちないように歩く)
- 忍者ジャンプ(障害物を飛び越える)
これらの動きは、子どもたちの瞬発力、バランス感覚、柔軟性、俊敏性などを自然と鍛えることができるのです。こどもたちは「忍者の修行」という設定で楽しみながら、実は重要な運動能力を身につけていきます。

忍術=スキル習得?子どもは「技をマスターすること」に快感を覚える
子どもにとって「技を習得する」というプロセスは、大きな達成感と自己肯定感をもたらします。忍者の技は、練習すれば少しずつ「できるようになる」という特徴があり、子どもたちの成長欲求に見事にマッチしています。
教育心理学者のエリクソンは、学童期の子どもたちが「有能感」を獲得することの重要性を説いていますが、忍者の技の習得はまさにこの有能感を満たしてくれるものです。折り紙で手裏剣を作るスキルを身につけたり、バランス感覚を必要とする「忍者歩き」ができるようになったりすることは、子どもの自信につながります。
Webサイトナショナルジオグラフィック掲載の「Is your kid always ‘in the zone’? That’s likely a mental health boost.」によれば、子どもは新しいスキルを獲得する過程で「フロー状態」と呼ばれる没入感を経験することがあり、これが脳の報酬系を活性化させ、さらなる学習意欲につながるとされています。
忍者の技の習得過程は、この「フロー状態」を生み出しやすい構造になっています:
- 明確な目標がある(例:手裏剣を的に当てる)
- すぐにフィードバックが得られる(当たった・当たらない)
- 難易度が調整できる(距離を変える等)
このような特性から、子どもたちは忍者の技を習得する過程で「できた!」という達成感を味わいやすく、それが「もっと上手くなりたい」という内発的動機につながります。
子どもが忍者にハマるのは成長の証?
子どもたちの忍者への強い興味は、単なる「かっこいいから好き」という理由を超えた、深い意味を持っています。発達心理学の観点から見ると、子どもが忍者に夢中になる時期は、自立心が芽生え始める重要な成長段階と重なっていることがわかります。
忍者ごっこに熱中する子どもたちの姿は、実は彼らの内面で起きている大きな変化のサインかもしれません。こどもの成長過程において、忍者という存在が特別な意味を持つ理由を探ってみましょう。
「忍者=自立心の象徴」!子どもは成長するにつれ「一人でできる」が嬉しくなる
3〜6歳頃の子どもたちは、「自分でやりたい」という気持ちが強くなる時期です。この頃の子どもにとって、忍者は「一人で任務をこなす」「自分の力で困難を乗り越える」存在として映ります。
子どもが「忍者になりたい!」と言うとき、その裏側には「自分も一人で何かをやり遂げたい」という自立への憧れが隠れています。発達心理学者のエリクソンが提唱した発達段階では、幼児期は「自律性 vs 恥・疑惑」の時期とされており、自分で物事を成し遂げる喜びを感じ始める大切な時期です。
4〜5歳の子どもは「秘密の行動」や「特別な能力」に憧れを持ち始め、それが忍者への興味につながるケースが多いとされています。
また、忍者を題材にした絵本や児童書が子どもの自立心を育むのに効果的だという結果も出ています。MY STELLA(マイステラ)のような親子向け情報サイトでも、子どもの成長に合わせた「忍者」関連コンテンツが人気を集めているのはこのためでしょう。
「忍者は修行する」→ 努力して強くなれる=成長の楽しさを教えてくれる
忍者の物語には必ず「修行」や「鍛錬」のシーンがあります。子どもたちはそんな忍者の姿から、「努力すれば成長できる」という大切なメッセージを受け取っています。
努力して少しずつ上達していくプロセスを体感することは、子どもにとって成長する喜びを知る貴重な経験です。心理学者のドゥエックが提唱する「成長マインドセット」の形成にも繋がる重要な学びと言えるでしょう。
忍者ごっこの中で「今日は昨日よりも高く跳べた!」「前よりも隠れるのが上手になった!」という小さな成功体験を積み重ねることで、子どもたちは「自分はがんばれば成長できる」という自己効力感を身につけていきます。
忍者の修行から学ぶ「成長マインドセット」
「忍者ごっこ」などのロールプレイを通じて「修行→成長」のプロセスを体験した子どもたちは、困難な課題に対しても粘り強く取り組む傾向が強まると言われています。
例えば、手裏剣を折り紙で作って投げる練習をする、バランス感覚を鍛える修行をするなど、忍者の世界観を通して「少しずつ上達していく喜び」を体験することができます。これは子どもの「非認知能力」の発達にも良い影響を与えると考えられています。
例えば、ファンタジー要素を含むロールプレイ(忍者ごっこを含む)が、幼児の「やり抜く力」(グリット)の発達に貢献するという結果も報告されています。
「秘密基地」「隠れる遊び」が好きなのも忍者好きと関係がある?
子どもたちが大好きな「秘密基地づくり」や「隠れんぼ」といった遊びと、忍者への興味には深い関連性があります。どちらも「秘密」や「隠れる」という要素を共有しているからです。
子どもが「秘密の場所」を持ちたがるのは、大人から離れた自分だけの空間を確保することで、精神的な自立を試みている証拠なのです。児童心理学者のワトソンは、秘密基地づくりは「自己コントロール感」を育む重要な活動だと指摘しています。
秘密基地と忍者の隠れ家に見る共通点
子どもが作る秘密基地と忍者の隠れ家には、次のような共通点があります:
| 特徴 | 子どもの秘密基地 | 忍者の隠れ家 | 心理的な意味 |
|---|---|---|---|
| 隠れる | 大人の目から隠れる | 敵から身を隠す | 安全感・自己保護能力の獲得 |
| 秘密 | 友達だけが知っている | 仲間だけが知る拠点 | 所属感・特別感の体験 |
| 自分たちのルール | 基地での独自のルール | 忍者の掟 | 自律性と社会性の両立 |
| 独自の言葉 | 秘密の合言葉 | 忍者の暗号 | アイデンティティの形成 |
国立青少年教育振興機構の調査によると、子どもの頃に創造的な遊びを経験した人は、大人になってからの問題解決能力や創造性が高い傾向にあることがわかっています。
絵本『きのうえのおうちにようこそ』(偕成社)など、子どもの秘密基地を題材にした作品が多く出版されているのも、この遊びが持つ普遍的な魅力と発達的意義を示していると言えるでしょう。
また、日本の伝統的な忍者の歴史を扱った子ども向けの博物館展示なども人気を集めており、伊賀流忍者博物館では子ども向けの忍者体験プログラムも充実しています。このような体験型学習は、忍者の世界観を通して歴史や文化への興味を育むきっかけにもなります。
子どもたちの忍者への夢中は、単なる一過性のブームではなく、彼らの自立心や挑戦する気持ちの表れと言えるのではないでしょうか。私たち大人は、そんな子どもたちの忍者好きを、成長の喜ばしいサインとして温かく見守り、応援していきたいものです。

「忍者好き」を全力で応援しよう!
子どもが忍者に夢中になったとき、それは単なる「好き」という感情を超えた、成長のチャンスです。親や教育者は、この興味をさらに深め、広げるサポートをすることで、子どもの可能性を大きく広げることができます。
子どもの「好き」を尊重し、それを学びや成長につなげる姿勢が、子どもの自己肯定感を高めます。忍者への興味を「ただの遊び」と軽視せず、そこから広がる学びの可能性を見つめることが大切です。
たとえば、忍者をテーマにした絵本は、忍者の世界観を楽しみながら、協力や工夫の大切さを学べる内容になっています。また、伊賀忍者博物館や甲賀流忍術屋敷などの史跡訪問は、歴史学習と冒険心を同時に満たす体験となるでしょう。
「忍者の知恵」は大人になっても役に立つ!?
忍者が身につけていた様々な技術や考え方は、実は現代社会を生きる上でも非常に価値のあるものです。子どもの頃に触れた「忍者の知恵」は、大人になっても活きる力となります。
忍者が大切にしていた「臨機応変」「冷静な判断」「持続力」などの資質は、社会人として求められる能力と重なる部分が多いのです。子どもが忍者に憧れることで、こうした資質の土台が自然と育まれていきます。
| 忍者の知恵 | 子どもの頃の体験 | 大人になって活きる場面 |
|---|---|---|
| 状況観察力 | 周囲を注意深く見て隠れる場所を探す | ビジネスでの情勢分析、問題の早期発見 |
| 持久力 | 長時間同じ姿勢を保つ修行 | 困難なプロジェクトの継続、ストレス耐性 |
| 臨機応変の対応 | 予期せぬ障害を乗り越える遊び | 突発的な問題への対処能力 |
| 創意工夫 | 身近なもので忍者道具を作る | 限られたリソースでの問題解決力 |
文部科学省のキャリア教育の指針でも、子どもの頃から「課題対応能力」や「自己管理能力」を育むことの重要性が指摘されています。忍者ごっこや忍者への興味は、こうした能力を楽しみながら培う絶好の機会と言えるでしょう。
このように、忍者の魅力は子どもの一時的な興味に留まらず、成長の各段階で様々な能力を育み、大人になっても活きる知恵や価値観の形成に貢献しているのです。だからこそ、子どもの「忍者好き」は単なる一過性のブームではなく、成長を支える重要な要素として尊重されるべきなのです。
まとめ
忍者の世界には、子どもたちの想像力を育むたくさんの魅力が詰まっています。忍者の歴史を知ることで、ただの「カッコいい」存在ではなく、知恵と工夫、忍耐強さを備えたスペシャリストだったことがわかります。
次回は、忍者の技術と能力について深掘りし、現代の子育てに活かせる知恵をご紹介します!