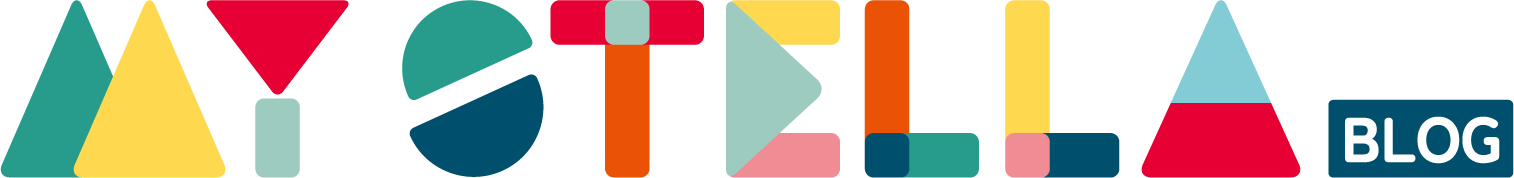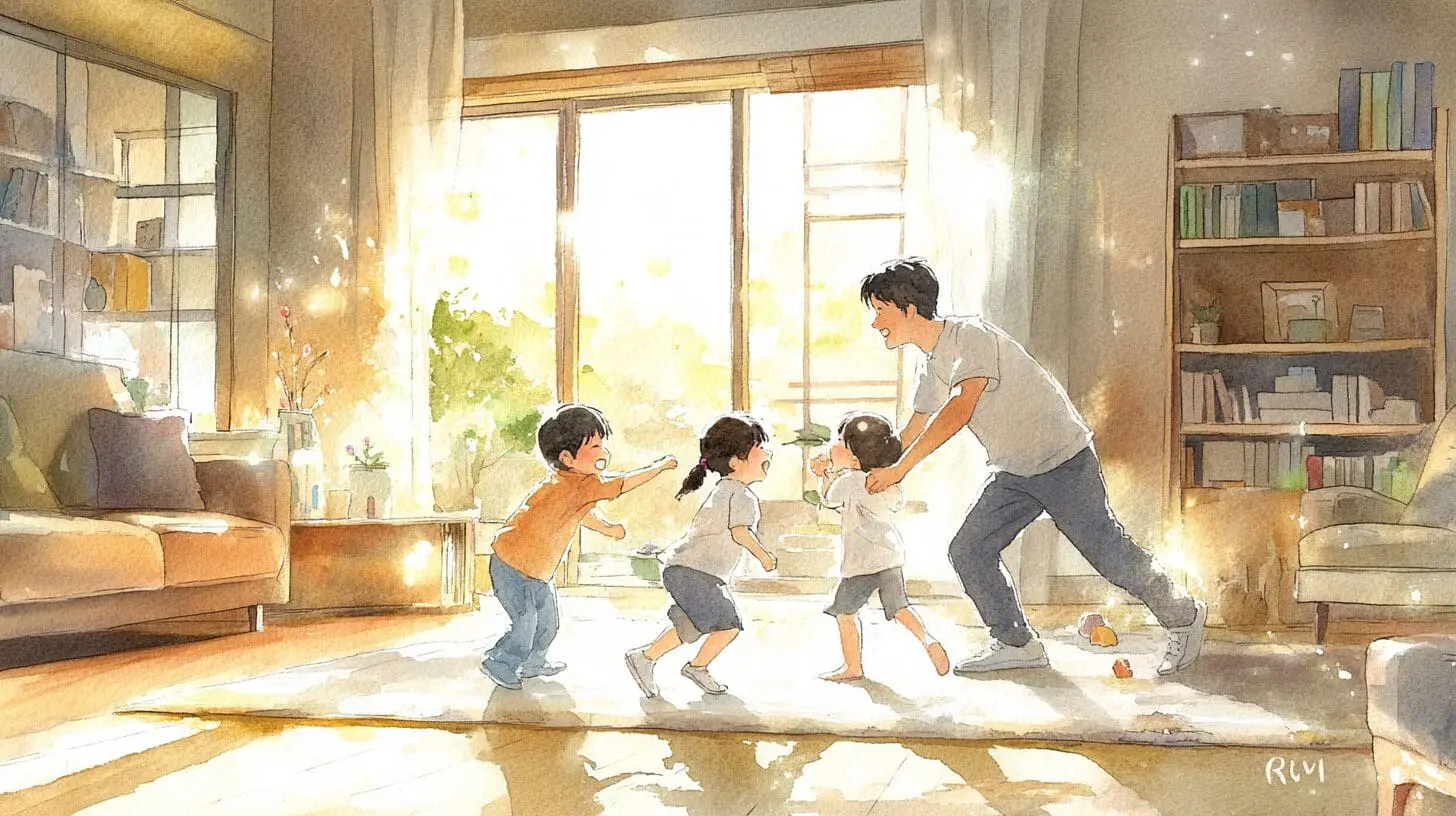こんにちは、マイステラ(MY STELLA)です!「親子の絆を深め、子どもの自己肯定感を育む」をモットーに、前回までは忍者の歴史と知識について更に深く紐解いてきました。
第3回となる今回は、忍者が持っていた素晴らしい技術と知恵に焦点を当て、それらをどのように現代の子育てに活かせるかをご紹介します。「忍者ごっこ?ちょっと大げさじゃない?」なんて思うかもしれませんが、これが本当に子どもの能力開発に役立つんです!実際に我が家で試してみて、子どもたちの成長ぶりに本気で驚きました。今回はそんな「マジで使える」忍者の知恵をお届けします!
忍術の基本〜五行の術から学ぶ子どもの「観察力」と「適応力」
忍者の技術体系「忍術」は、単なる身体技術ではなく、情報収集や生存のための総合的な知恵の集大成でした。特に「木・火・土・金・水」の五行に基づいた世界観は、子どもたちの観察力と思考力を育む素晴らしい教材となります。
例えば、木の術は成長と柔軟性を象徴し、自然の力を利用する技術。水の術は流動性と適応力を象徴し、状況に合わせて形を変える発想法を教えてくれます。
うちの5歳の息子に「今日は雨が降っているね。忍者なら、この状況をどう活かすかな?」って聞いたら、「雨の音で足音を隠せる!」って即答したんです。**まじでっ!**どこでそんなこと覚えたの?って驚きました。子どもの発想力って本当にすごい!
**2月22日は「忍者の日」**ということをご存知でしょうか?2(に)2(に)2(に)で「にんにん(忍忍)」の語呂合わせから制定されたこの日は、各地の忍者関連施設で特別なイベントが開催されます。家族でこの日を「忍者の腕試しの日」と決めて、年に一度の特別な体験を積み重ねるのも素敵な家族の思い出になるでしょう。
🥷 忍者の変装の術〜子どもの想像力と社会性を育む
忍者が得意とした「変装の術」は、子どもの想像力と社会性を養う絶好の教材です。忍者は任務に応じて農民、商人、旅芸人など様々な姿に変装しましたが、これは単なる衣装の変更ではなく、その職業や立場になりきる深い観察と演技が必要でした。
三重県伊賀市にある「伊賀流忍者博物館」では、実際に忍者が使った変装の技術や道具が展示されています。同博物館の学芸員によれば、「忍者は相手の目線や思考パターンを理解することで、完璧な変装を実現していた」とのこと。これはまさに現代の「共感力」「他者理解」に通じる能力です。
お家でできる!変装遊びのススメ
家にある服や小物を使って様々な職業に変身するごっこ遊びがおすすめです。「お医者さんならどんな言葉を使うかな?」「図書館の人はどんな動き方をするかな?」と問いかけながら、他者の視点や行動パターンを理解する力を育みましょう。
小学生の頃、友達と「変装忍者ごっこ」をして遊んでいました。母のスカーフや帽子を借りて、近所のおばあちゃんの家に忍び込もうとしたら、おばあちゃんが「あら、○○ちゃんたちじゃない?」って即バレ。確かに服装だけじゃなくて、歩き方や話し方まで変えないと本当の変装にならないんですよね(笑)。今思えば、当時はただの遊びだと思っていましたが、実は他者の行動パターンを観察する貴重な練習だったんですね!
「忍者保育」という言葉を聞いたことはありますか?一部の保育園では、この「変装の術」の考え方を取り入れた「なりきり遊び」を通じて、子どもたちのコミュニケーション能力や社会性を育む取り組みが注目されています。
💡 忍者の道具(忍具)から学ぶ創意工夫の心
忍者は様々な道具(忍具)を駆使して任務を遂行しました。有名な手裏剣や苦無(くない)のほかにも、縄や鎌を組み合わせた「鎖鎌」、水中呼吸のための「水蜘蛛」、壁を登るための「鉤縄」など、目的に応じた道具を巧みに使いこなしました。
これらの忍者の道具は、単なる武器ではなく、知恵と工夫の結晶でした。手元にある限られた素材から最大限の効果を生み出す発想は、子どもたちの創造性と問題解決能力を育むのに最適です。
滋賀県甲賀市の「甲賀流忍術屋敷」では、実際に使われていた忍具の展示だけでなく、その使い方や工夫の秘密を学べます。学芸員の方によると「忍者の道具は一つ一つが軽量でコンパクト、かつ複数の用途に使える多機能設計だった」そうです。まさに現代のミニマリストやサステナブルな価値観の先駆けと言えるでしょう。
わが家でできる!超簡単忍具作り術

段ボールや空き箱、毛糸などの身近な材料を使って、オリジナルの忍者道具を作る活動がおすすめです。「この道具はどんな時に役立つ?」「どうすればもっと便利になる?」と子どもに問いかけることで、創造性と論理的思考力が自然と育まれます。
先日、うちの6歳の娘と「忍者の道具」を作りました。トイレットペーパーの芯と輪ゴムで「望遠鏡」を作ったはずが、娘が「これはね、敵を眠らせる眠り笛だよ!ふーっ」って吹きはじめて。そのあと本当に夫が爆睡しちゃって(笑)。**本当に!?**って、子どもの創造力って無限大ですね!
特に雨の日の室内遊びとして、「忍者の巻物」を作るのも楽しい活動です。画用紙を丸めて棒を両端に付け、そこに「忍者の秘密の技」を描いたり書いたりする遊びは、文字への興味も引き出します。これこそが本物の「忍者の巻物」、子どもたちの創造性の宝庫となるでしょう。
🔍 情報収集の技〜子どもの注意力と記憶力を養う
忍者の真骨頂は、実は情報戦にありました。敵地に潜入し、重要な情報を収集・記憶し、持ち帰る―この能力は、情報があふれる現代社会を生きる子どもたちにこそ必要なスキルです。
家族で楽しむ!忍者情報収集ゲーム
買い物や散歩に行ったときに「忍者のように、この店の赤い物をすべて観察してごらん」「公園で聞こえる音を3つ覚えてきて」といった小さな任務を与えてみましょう。「ミッションクリア!」と成功体験を重ねることで、子どもの自己肯定感が高まります。
実は、うちの子は発達障害気味で集中力が続かないことが悩みでした。そこで「忍者のスパイミッション」として買い物中にお店の情報を集める任務を出してみたんです。最初は適当にやっていた息子が、だんだん真剣になってきて、最後には店員さんの名札まで覚えてきて。「パパ、あのお姉さんの名前は○○だよ!」って得意げに報告してくれた時は、思わず涙が出ました。**こんなに集中できるんだ!**って。忍者って、本当に子どもの可能性を引き出してくれるんですね。
親子で「忍者の森」探検と題して、自然の中で五感を使った観察訓練をするのもおすすめです。「この葉っぱはどんな匂いがする?」「どんな虫が隠れているかな?」と問いかけながら、子どもの感覚を研ぎ澄ませていきましょう。三重県や愛知県には「忍者の森」と名付けられた自然体験スポットもあります。名古屋市近郊の「忍者の森」では、自然の中で本格的な忍者修行ができると家族連れに人気です。
💪 忍者の身体技術〜運動能力と自己コントロール力
忍者の身体技術は、決して超人的なものではなく、徹底した訓練による基礎体力と正確な動作の積み重ねでした。
今すぐ始める!3つの忍者トレーニング
家庭でできる身体技術トレーニングとしては、以下のような簡単な「忍者修行」がおすすめです:
- 忍者歩き:音を立てずにそっと歩く練習(集中力と身体制御)
- 壁歩き:壁に背中をつけてしゃがみ込み、ゆっくり横に移動(バランスと下半身強化)
- 忍者ブリッジ:四つん這いになって腰を高く上げ、その姿勢で前進(全身の協調性)
これらの動きは特別な道具がなくても室内で安全に実践でき、子どもの運動能力を総合的に高めます。「忍者のように」というフレーズを使うだけで、子どもたちは夢中になって取り組むでしょう。
子どもの頃、『ドラゴンボール』に影響されて「気配を消す」訓練をしていました。廊下を音を立てずに歩く練習をしていたら、突然母に「そこにいるのわかってるよ」って言われて超ショック(笑)。子どもの頃こんなことしたよね、みんな。今、自分の子どもと「忍者歩き」をすると、あの頃の気持ちがよみがえります。でも今度は「おぉ!息子の気配が消えてる!」ってセリフが大人の役目です。
📚 忍耐力と集中力〜精神力を養う忍者の教え
忍者の「忍」の字が示す通り、「心に刃を当てて耐える」という忍耐の精神は、忍者の根本にありました。この精神力こそ、現代の子どもたちにも必要な「困難を乗り越える力」に直結します。
忍者の絵本を活用するのも効果的です。最近では、忍者を題材にした絵本や書籍も多く出版されています。「忍者の絵本」を通じて、忍者の忍耐強さや知恵を学ぶことができます。寝る前の読み聞かせに取り入れてみてはいかがでしょうか。特に主人公が困難を知恵と忍耐で乗り越えるストーリーは、子どもの心に深く残るでしょう。

先日、4歳の息子に忍者の絵本を読み聞かせていたら、「忍者は諦めないんだね」って言われました。最近、自転車の練習で何度も転んで泣いていた息子が、次の日「ぼく、忍者みたいに諦めないよ!」って自分から練習したがるように。一週間後には補助輪なしで乗れるようになりました。絵本の力ってすごい!息子の成長に涙が出ました。
マイステラでは、まもなくオリジナルの「忍者の絵本」が発売予定です。お子さま一人ひとりに合わせたパーソナライズ絵本で、忍者の世界を通して「諦めない心」や「工夫する力」を学ぶことができます。ぜひお楽しみに!
⚔️ 子どもに伝えたい!意外と知られていない忍者の真の強さ
忍者の真の強さは、武器や戦闘技術ではなく、「適応力」と「判断力」にありました。敵地で孤立した状況でも冷静に判断し、その場に応じた最適な行動を選択する―これこそが忍者の核心的な能力です。
戦前から戦後にかけて忍術研究の第一人者として活動していた藤田西湖氏は「忍者は単純な勝ち負けではなく、いかに目的を達成するかを第一に考えた。時には戦わないことが最高の戦略だった」と語っています。この「状況に応じた最適解を見つける」考え方は、複雑な現代社会を生きる子どもたちにこそ必要なマインドセットです。
先日、小学生の息子が友達とケンカして、「やり返さなかった」と言うので、最初は「なんで逃げたの?」って思ったんです。でも息子は「だって戦うより、仲直りする方が大事だし、一番の忍者は戦わないで任務を成功させる人なんだよ」って。**まじか…!**子どもから逆に人生の教訓を教えられた気分でした。
🏠 お家でできる忍者ごっこ〜5つの実践アイデア
最後に、今日からすぐに実践できる「忍者ごっこ」をご紹介します。これらの遊びは特別な道具がなくても始められ、子どもの様々な能力開発に役立ちます。
明日からすぐできる!忍者遊び5選
- 忍者の暗号伝言:簡単な暗号を作り、家族間で秘密のメッセージを交換する遊び(論理的思考と創造性)
- 影忍び:LEDライトなどを使って壁に映した影から逃げる、または追いかけるゲーム(身体認識と空間把握能力)
- 忍者の隠れ家作り:毛布や椅子を使って室内に秘密基地を作る活動(創造力と問題解決能力)
- 五感トレーニング:目隠しをして音や匂い、触感だけでものを当てる遊び(感覚統合と集中力)
- 忍者の迷路ミッション:部屋の中に障害物を置き、ひもなどで「レーザートラップ」を作って、それらを避けながら「秘宝」(おもちゃなど)を取りに行くゲーム(身体コントロールと空間認識)
先日、「忍者の迷路ミッション」を家でやってみました。リビングに赤い毛糸を張り巡らせて「レーザートラップ」を作りました。子どもたちは大喜びで挑戦していたんですが、夜中にトイレに起きた夫が真っ暗な中で毛糸に引っかかって大転倒! 「な、何が起きたんだーーー!!」って叫んで家族全員起こしちゃって。**まじで笑った!**でも翌朝、夫も「忍者の修行が足りなかった」と言って一緒に遊びはじめたのが最高のオチでした♪
これらの遊びに「忍者の巻物」で作った特別なミッション指令を加えると、さらに本格的な忍者体験になるでしょう。「今日の任務は…」と書かれた巻物を朝食時に渡すだけで、一日中子どもが夢中になって取り組む姿が見られるかもしれません。

まとめ:忍者の知恵で育む「生きる力」
忍者の技術や考え方は、単なる歴史上の存在ではなく、現代の子育てに活かせる貴重な知恵の宝庫です。観察力、適応力、問題解決能力、創造性、身体能力、忍耐力、協調性…忍者が持っていたこれらの能力は、まさに現代社会を生き抜くために必要な「生きる力」そのものです。
忍者の世界を通して、お子さんの想像力と自己肯定感を育む旅を楽しんでください。子どもたちが自らの力で問題を解決し、どんな状況でも柔軟に対応できる力を身につけられるよう、忍者の知恵を現代の子育てに活かしていきましょう。
次回予告
次回は「親子で行く!忍者体験スポット特集〜本物の忍者の世界を体感しよう」と題して、全国の忍者博物館や体験施設をご紹介します。実際に手裏剣投げや忍者衣装体験ができる場所、本格的な忍者修行が体験できるスポットなど、家族で楽しめる忍者の聖地をご案内します。お楽しみに!