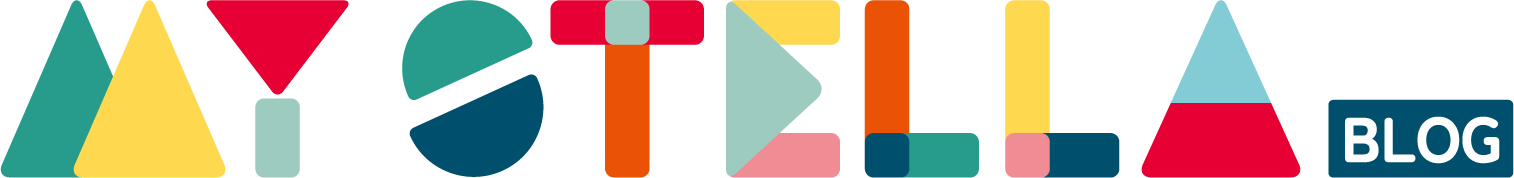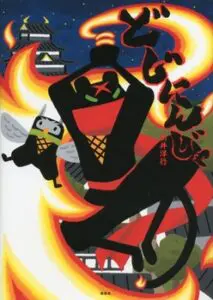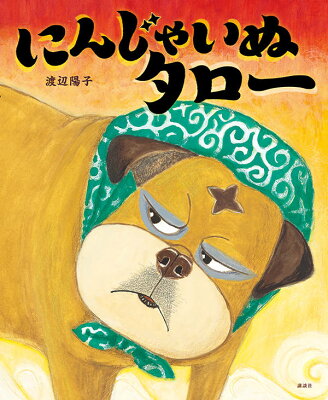「パパ、忍者になりたい!」
息子がそう言い出したのは、確か4歳の頃でした。保育園で忍者ごっこが流行っていたようで、家でも毎晩のように手裏剣を投げる真似をしたり、畳の上で前転したりと、もう家中が道場状態。
そんな時、何気なく図書館で手に取った一冊の忍者絵本が、親子の時間を大きく変えてくれました。絵本を読んだ後は必ず「忍者修行」が始まり、私も童心に返って一緒に追いかけっこや忍者遊び。仕事の疲れも吹き飛ぶ、かけがえのない時間になったんです。
今回は、そんな親子の絆を深めてくれる「忍者絵本」を21冊、年齢別にご紹介します。何歳になっても魅力的な忍者がテーマの絵本、それぞれの作品の魅力を余すことなくお伝えします。
なぜ今、忍者絵本なのか
忍者という存在は、子どもたちにとって魔法のような存在です。多くの子どもたちが夢中になる忍者。彼らは、空を飛び、壁を登り、影に隠れる——そんな超人的な能力への憧れは、想像力を無限に広げてくれます。
でも、忍者絵本の魅力はそれだけではありません。
努力と修行という要素が自然に物語に織り込まれているから、「頑張ること」の大切さを押し付けがましくなく伝えられるんです。失敗しても何度も挑戦する姿、仲間と協力する場面、目標に向かって諦めない心——これらは、絵本を通じて子どもの心に静かに根付いていきます。
印刷業に携わる私たちは、「残すこと」の価値を知っています。絵本という形で残された物語は、読むたびに新しい発見をもたらし、親子の会話を生み出し、やがては一生の思い出になる。そんな一冊との出会いを、このガイドでお手伝いできれば嬉しいです。

0〜3歳向け|はじめての忍者絵本
①「おりがみにんじゃ」つきおかゆみこ・作|折り紙×忍者の遊びと変身がぎっしり詰まった絵本
おりがみにんじゃは、折り紙で鳥や恐竜などに変身して「あずき城」の宝を探す冒険絵本です。お姫さまが和菓子で戦う場面など、ユニークでほっこりする展開が続きます。
折り紙の折り方も絵本に掲載されていて、読みながら実際に折り紙遊びができる仕掛け付き。
子どもたちの創造力と指先の発達を促すと同時に、「変身」という忍者のワクワクがいっぱい。
絵探しと折り紙の楽しさを両立し、親子で参加型で楽しめる構成。
折ることでどんどん変身!忍者ならではのすばやい変わり身が楽しく、物語と工作が一体となった珍しい絵本として人気です。読者レビューでも、家族で折って遊びながらストーリーを進める時間が好評です。
②「にんじゃべんとう」木坂涼・作、いりやまさとし・絵|忍者ごっこと食育が楽しめる一冊
にんじゃおにぎり三兄弟が「にんじゃむら」でお弁当に入るいろいろなおかずを集めながら、楽しい忍法を繰り広げていく絵本です。忍者たちがアスパラベーコン、エビフライ、コロッケなどを忍法で作りながら、お弁当をどんどんにぎやかにしていきます。
リズミカルな文章とかわいらしいイラスト、忍法ごっこをしながら食材の名前やお弁当のおかずを自然に覚えられる構成
オノマトペや忍者らしい言い回しがテンポよく繰り返され、小さな子どもと一緒に遊びながら食材や料理名を覚えられる点が親子紹介でも特に好評です。 簡単なストーリーにミニゲーム要素もあり、幼稚園〜年中さん未満の子どもに最適。読み聞かせや食育のきっかけにもなる楽しい一冊です。
③「おにぎりにんじゃ」北村裕花・作|身近な食べ物が忍者に!
おにぎりが忍者になって、不思議な術でピンチを乗り越えていく——そんなユニークな発想が光る一冊。身近な食べ物が主人公だから、幼児でもすぐに親しみを感じられます。
見る度に新しい発見があるイラストは秀逸で、「どうやって今度は隠れる?」と親子で語りかけながら楽しめる仕掛けが満載。単純な繰り返し構成なので、読み聞かせの負担も少なく、寝かしつけにも活躍してくれます。
我が家では食卓で「おにぎり忍者」と盛り上がったり、お弁当作りの時にも話題になって会話が自然と増えました。子どもが食べ物に興味を持つきっかけにもなり、「これも忍者になれる?」なんて質問が飛び出すように。想像力を育む入口として、本当に良い絵本だと思います。
④「いかにんじゃ」みきすぐる・作|ユニークすぎる海の忍者
読んでいるとだじゃれがたくさん出てきて、自然と笑いがこみ上げてきます。子どもたちはもちろん、大人も思わず「そんな忍術あり?」とツッコミを入れながら楽しめる作品です。
イカの忍者が海の中で不思議な術を駆使して冒険する物語です。カラフルでユーモアあふれるイラストはおおのこうへいさんが担当し、そのリズム感あふれる文章はみきすぐるさんの作です。
この絵本を読んだ後は、子どもが「イカ忍者」のマネをしてユニークな動きをすることが多く、家族みんなで笑顔になること間違いなしです。お風呂の時間にも「いかにんじゃー!」と叫びながら遊び、日常生活の中で一層楽しい時間を過ごせるようになりました。だじゃれが好きな子どもや忍者好きの小学生に特におすすめです。
⑤「にんじゃじゃ!」岡本よしろう|仕掛けいっぱいの体感型絵本
忍者と殿様の追いかけっこがテンポ良く展開し、何度も探しては隠れる忍者の姿に子どもたちは夢中になること間違いありません。見返しには忍者の道具や秘密の迷路もあり、読み聞かせ後の遊びにも広がります。
眠っていた殿様の秘蔵のちょんまげが盗まれた!大騒ぎのお城の中で、家来たちが必死に忍者を探し出します。瓦屋根を走り抜け、隠れ蓑で姿を隠し、あらゆる忍具を駆使する忍者の身の軽さと技に惹きつけられます。また、歌のようなリズム感で言葉が繰り返され、読み手も子どももノリノリで楽しめる絵本です。
忍者の身のこなしや技の多様さにワクワクし、忍者ごっこ遊びのきっかけになる絵本です。息子が忍者ブームの時に夢中で読んでいました。声に出して読んで、読んで、探して、笑って、遊んで親子で盛り上がれる絵本。読み終わったあとは家中で‘にんじゃはどこじゃ?’って探しっこが始まります。親もつい夢中になってしまうテンポの良さと探し要素が良いですね。巻末の迷路で一緒に遊べるのもポイントです。
⑥「かむにんじゃ参上!」いろは作/うさみたまえ絵|たのしくよく噛んで食べる食育絵本
いろはさん作、うさみたまえさんが絵を担当する「かむにんじゃ」シリーズの第3弾。主人公のかむにんじゃが、リズムに合わせて「ひとくち30回」よく噛んで食べることの大切さを楽しく教えてくれます。
物語は、たあくんが大好きなにんじん蒸しパンをあわてて食べて喉に詰まらせてしまうところから始まります。そこに「かむにんじゃ」が颯爽と参上!「かむこと」の大切さを教える忍法リズムの術を伝授してくれるのです。この絵本の最大の特徴は、リズミカルな言葉と歌(かむにんじゃのうた「かむかむメロディー3」)が盛り込まれていること。子どもたちが自然とよく噛む習慣を身につけられるよう、楽しく工夫されています。
読み聞かせをしながら親子で一緒にリズムに乗って、食事時間を楽しくする——まさに「遊び」と「学び」が融合した食育絵本です。我が家でも、この絵本を読んでから「かむかむメロディー」を口ずさみながら食事をするようになり、自然とよく噛む習慣が身につきました。忍者という子どもが大好きなテーマと、親が伝えたい「食育」がうまく組み合わさった、まさに理想的な一冊だと感じています。
⑦「どんぐりにんじゃ」浅沼とおる・作|自然との触れ合いを学ぶ
森のどんぐり忍者が仲間と共に冒険する物語。自然の中で協力する大切さを教えてくれます。
森や川、動物にも興味がわき、外遊び好きな家庭に最適。協力し合うことの楽しさを親子で確認できる構成です。
自然とのふれあいを絵本を通じて考えさせてくれる作品。家族で森へ出かけたくなる一冊です。実際に、この絵本を読んでから近所の里山にどんぐり拾いに行くようになり、季節の移り変わりを親子で感じる時間が増えました。

4〜5歳向け|冒険心と勇気を育む忍者絵本
⑧「にんじゃつばめ丸」市川真由美|家族の絆を感じる名作
ごく普通の家庭が実は忍者一家だった…という、子どもの夢を広げる設定が魅力。夜の修行や運動会での勇気と努力が描かれるストーリーで、家族みんなで頑張る姿が印象的です。
親子で「自分が忍者だったら」と想像する時間が自然と増え、家族の会話が深まります。
運動会前にこの絵本を読んだら、息子が「ぼくも忍者みたいに頑張る!」とやる気を出してくれました。家族の絆、勇気、努力が自然に伝わる名作です。MY STELLAで「家族の物語」を大切にしている私たちにとって、この絵本の価値観はとても共感できるものでした。
⑨「てのりにんじゃ」山田マチ・作、市居みか・絵|親子で忍者修行が始まる
小さい手乗り忍者が冒険するお話。幼児の手に収まりやすいサイズ感で描かれているから、「自分も忍者になれそう!」という気持ちが自然に芽生えます。
簡単な術の説明も親子で真似したくなるポイント。自分が主人公の忍者になった気分で遊べるので、親子のコミュニケーションが驚くほど活発になります。
息子がまるで自分が主人公の忍者になったかのように、部屋中で修行を始めたんです。親子で追いかけっこしたり、忍術大会が毎晩開催されるようになりました。体をよく動かすので、寝つきも良くなって一石二鳥。絵本一冊でこんなに遊びが広がるとは思いませんでした。
⑩「わんぱくだんのにんじゃごっこ」ゆきのゆみこ|冒険ファンタジーの決定版
人気シリーズの忍者編。タイムスリップした子どもたちが姫を助けるという冒険ファンタジーで、実際の遊びに結びつきやすい構成が特徴です。
読後は必ず忍者ごっこが始まると言われるほど、遊びに発展させやすい作品。冒険心をくすぐる展開に、父親も童心に返ってしまいます。
「姫を助けろ!」と叫びながら部屋で忍者ごっこをする息子の姿を見て、仕事の疲れも吹き飛びました。親子で冒険するきっかけになる絵本。休日の公園でも忍者ごっこが定番になり、他の親子も巻き込んで盛り上がっています。
⑪「どじにんじゃ」藤本ともひこ・作、村田エミコ・絵|失敗を恐れない心を育てる
失敗ばかりの忍者が何度も挑戦する姿が描かれるユーモラスな絵本。コメディ要素が強く、失敗=成長というメッセージを自然に伝えてくれます。
親子で「どうやったら成功する?」と一緒に策を考える時間が面白い。忍者なのにドジというギャップが、子どもの心をぐっと掴みます。
子どもが「ぼくも失敗してもいいんだ!」と励まされていました。笑いながら前向きになれる絵本。完璧を求めすぎる現代の子育てにおいて、この「失敗していいんだよ」というメッセージは本当に大切だと思います。
⑫「にん・にん・じんのにんじんじゃ」うえだしげこ|ユーモア満載の冒険絵本
トマトやしいたけといった野菜や食べ物キャラクターが登場し、だじゃれを織り交ぜた楽しい物語です。
修行を怠けて遊んでばかりのだめ忍者「にんじんじゃ」が主人公。殿様から、剣の達人しいたけんしを探す大事な役目を命じられますが、失敗連続でユーモア満載の冒険を繰り広げます。
そして、これもまた、ダジャレが多くて微笑ましい気持ちになる絵本です。忍者とダジャレは相性がいいのでしょうか。リズミカルで語りやすい文体は親子で声に出して読むのにぴったり。言葉遊びやだじゃれ満載で、語彙力アップや読み聞かせの笑いの創出に最適。シリーズ展開しており、はじめての忍者絵本としても楽しめる。息子が読み始めてから、だじゃれをよく言うようになりました。だめダメ忍者のキャラクターが面白く、読み聞かせも明るい気持ちになれます。家族で声を合わせて読むのが楽しいです
⑬「にんじゃサンタ」丸山誠司|にんじゃの技でクリスマスを駆け抜ける絵本
クリスマスイブの夜、日々修行を怠らず忍者として鍛錬するにんじゃサンタが、ひたすら走り、飛び、忍術を駆使して子どもたちにプレゼントを届ける物語です。
にんじゃサンタは、投げて、隠れて、もぐったりしながら、見つからないように素早くプレゼントを運ぶという新感覚のサンタクロース像を描いています。リズミカルな文章と躍動感あふれるイラストで、子どもたちの興味を引きつけ、読み聞かせにもぴったりです。
にんじゃサンタの訓練風景から始まり、ハンドベルの音が鳴るクリスマスイブにきがえて集合し、夜の街へ繰り出す様子は、忍者のスピード感とサンタのワクワク感が巧みに融合しています。丸山氏のカラフルでユーモラスな絵柄も魅力の一冊です。
この絵本は忍者とサンタが合体した斬新な発想で、クリスマスの特別な一夜を子どもたちと家族で楽しむのに最適です。普段のサンタクロースのイメージに新鮮な風を吹き込み、ユーモアと夢あふれるクリスマスを演出します。

6歳〜小学生向け|知的好奇心を刺激する忍者絵本
⑭「忍者にんにく丸」川端誠|野菜忍者の痛快救出劇絵本
川端誠さん作の絵本『忍者にんにく丸』は、「野菜忍列伝」の第一作目。青空晴高のけらいであるにんにく丸が、黒雲城の主・闇雲暗之輔にさらわれた飛子姫を救いに向かう物語です。
にんにく丸は腕利きの忍者で、姫を救うために敵方の忍者・強力麺蔵と激しい対決を繰り広げます。この戦いはスピード感と切れ味があり、忍者のアクションと野菜をモチーフにしたキャラクターの面白さが融合しています。
川端氏のユーモアと緊張感のバランスが絶妙で、子どもたちが忍者の世界に引き込まれる内容です。野菜キャラクターが登場することで、読み進めながら自然と食育や健康意識にもつながる要素が盛り込まれています。
絵は力強く鮮やかで、忍者アクションの躍動感が伝わりやすく、読み聞かせにも適しています。忍者好き、冒険好きの子どもにおすすめの一冊です。
⑮「にんじゃなんにんじゃ」中垣ゆたか|遊びながら忍者の秘密がわかる図鑑絵本
この本の魅力は、楽しいストーリーの合間に、忍者の歴史や忍術の仕組みが自然に学べる構成。まるで忍者屋敷を探検するように、ページをめくるたびに新しい発見があります。細かく描き込まれたイラストは、何度見ても飽きない工夫が満載です。
わかりやすい言葉とユーモアのある絵が組み合わさっているので、親子での読み聞かせはもちろん、小学生なら一人で読んでも楽しめる一冊。
忍者の魅力を多角的に紹介しながら、遊び感覚で知識が深まる——そんな体験を届けてくれる絵本です。忍者好きの子どもはもちろん、「学びと遊びを両立させたい」と考えるご家庭にぴったりの作品だと思います。
⑯「にんじゃにんじゅろう」舟崎克彦|忍者修行と家族の絆を描く幼年童話
ある日、忍者学校から帰宅したにんじゅろうは、両親が見当たらないことに気づきます。「これは自分を試すためのしかけだ!」——そう悟った彼は、屋敷に仕掛けられた様々なからくりや試練に挑んでいきます。
幼い子どもにもわかりやすい文章で、忍者の世界の楽しさはもちろん、家族の絆や努力と成長の大切さを優しく伝えてくれます。読み聞かせにも適したサイズとページ数で、親子で楽しめる一冊です。
飯野和好さんの力強く温かみのある絵が、にんじゅろうの成長を生き生きと描き出しています。「親に試される」という設定は、子ども心に「自分も認められたい」という気持ちを呼び起こし、自然と応援したくなる物語です。
息子もこの絵本を読んでから、「パパ、ぼくも試練に挑戦したい!」と言い出すようになりました。家の中に簡単な障害物コースを作って「忍者修行」をするなど、遊びに発展させやすい作品です。
⑰「あかにんじゃ」穂村弘|目立ちすぎる赤忍者の痛快ナンセンス絵本
全身真っ赤な忍者が主人公の『あかにんじゃ』。秘密の巻物を狙ってお城に忍び込みますが、その赤い姿のためにすぐに見つかってしまいます。
追い詰められた赤忍者は、「ドロンドローン」と呪文を唱えて次々に変身!でも、変身先もまた赤いものばかり——赤いカラス、赤いチョウチョ、そして最後には赤いおじさんにまで変わるという奇想天外な展開が、子どもたちに大人気です。
忍者らしい隠密行動というよりは、ナンセンスと笑いで彩られた楽しい物語。リズムにのった読み聞かせや繰り返しの呪文「ドロンドローン」が耳に残りやすく、子どもも大人も思わず笑ってしまう一冊です。
我が家では、この絵本を読んだ後、息子が「ドロンドローン!」と叫びながら家中を駆け回るのが定番になりました。「次は何に変身する?」と親子で予想合戦をするのも楽しい時間です。一緒に変身ポーズをして写真を撮るなど、家族イベントにも発展させやすい作品ですね。
穂村弘さんの詩人らしい言葉のリズム感と、木内達朗さんの鮮やかでスタイリッシュな絵が見事に融合。「赤」という色をテーマにした発想力が、子どもの想像力をぐんぐん育ててくれます。
⑱「すっぽんぽんのすけ」もとしたいづみ|裸のまま忍者と戦う元気な男の子
お風呂上がりの裸が一番!「すっぽんぽんのすけ」は、そんな元気いっぱいの男の子が主人公の絵本です。
忍者にさらわれた子猫のみいちゃんを助けるため、パンツをはかずにすっぽんぽんのまま町を駆け回り、忍者たちを蹴散らす——その痛快さが、子どもたちの心を鷲掴みにします。リズミカルで楽しい文章と、荒井良二さんの個性的で味わい深いイラストが見事に融合。読み聞かせで大人も子どもも巻き込む楽しさがあり、思わず笑顔になる一冊です。
子どもの自由な想像力の象徴として、裸でのびのびと冒険する姿が元気を与えてくれます。シリーズも展開しているので、気に入ったらぜひ続編も手に取ってみてください。
我が家でも読み聞かせ後、息子が「すっぽんぽんのすけ!」と元気に真似をして走り回る姿が定番になりました。お風呂上がりの時間が、まるで冒険タイムに変わったような感覚です。荒井良二さんの独特の絵が物語の世界を鮮やかに彩り、リズム感のある言葉が耳に残る——読み聞かせをする親の方も、自然とテンションが上がってしまう不思議な魅力があります。
1999年の発行以来、多くの支持を集めている人気作品。忍者絵本としても、元気が出る絵本としても、幅広い場面でおすすめできます。
最新作・番外編
⑲「にんじゃいぬタロー」渡辺陽子|忍者犬と少年のわくわく忍者修行絵本
第41回講談社絵本新人賞受賞。主人公の男の子ケンタの家に、ふろしきを背負い、おでこに手裏剣の模様がある怪しい犬「にんじゃいぬタロー」がやってきます。タローは主である「殿さま」を探していると言い、ケンタと一緒に殿さま探しの旅と忍者修行に出かける——そんなわくわくする冒険物語です。
物語の舞台は、忍者屋敷のように変わるケンタの家。忍者の修行や大冒険が楽しく描かれ、読み聞かせにぴったりのわくわくする展開が続きます。
生き生きとした水彩と色鉛筆の優しいタッチの絵が物語を彩り、子どもたちの想像力をかきたてます。講談社絵本新人賞受賞作品ならではの丁寧な描写と、温かみのある世界観が魅力です。
我が家でも、この絵本を読んだ後は必ず「タローごっこ」が始まります。「殿さまはどこだ!」と家中を探し回ったり、ぬいぐるみを忍者犬に見立てて修行ごっこをしたり——絵本から遊びへの広がりが自然に生まれる作品です。
すべてひらがなで書かれているので、小学校低学年なら自分で読むこともできます。「自分で読めた!」という達成感が、読書への自信につながる一冊としてもおすすめです。
⑳「忍者からみた世界」三橋源一・文、飯野和好・絵|実際に忍びが暮らした自然と日常から、本当の忍者を探る
アニメや小説で描かれる忍者ではなく、学術研究と忍術修行を重ねた著者が、リアルな伊賀の暮らしを通して「本当の忍者像」に迫ったノンフィクション絵本です。忍者は日々農作業や狩猟、薪割りなど自然の中の暮らしと密接に結び付きながら、「情報を持ち帰るために生き延びる」ことを最優先としました。忍術や武器の技は、実際の生活や環境から生まれ、田畑での歩き方や道具使いが忍者のスキルへと発展していったことが鮮やかに描かれています。
忍者の仕事や技の背景にある合理性・生きる力を、ドキュメンタリー風の語りと力強いイラストで伝える
子どもの好奇心や探究心を育てる科学絵本「たくさんのふしぎ」2025年9月号として発行
忍者が単なる戦いのスペシャリストではなく、日々の地道な暮らしの中からスキルや工夫が生まれた――そんな新しい視点が満載です。子どもに「忍者の本当の姿」を伝えたい家庭や、歴史・職業への興味を広げたい親子に最適の一冊です。
㉑「にんじゃラリーマン」丸山誠司|忍者会社員が繰り広げるお仕事コメディ絵本
忍者のサラリーマン“にんじゃラリーマン”たちが、会社で開発した夢の商品「にんじゃくん!セット」をめぐって大騒動を巻き起こすユーモラスな絵本です。「にんじゃくん!セット」は、誰でも忍者になれる4つの道具が入った新商品。ところが、完成をよろこぶ暇もなく泥棒に盗まれてしまい、にんじゃラリーマンたちは会社一丸となって大捕り物に挑みます。
ユーモラスな忍者会社の社内風景、テンポよく楽しいアクション、お仕事×忍者の発想が新鮮
失敗やピンチもみんなで協力して乗り越えるチームワーク描写があり、親子で大笑いしながら読める内容。
保育現場や読み聞かせイベントでも盛り上がるとして、多数の読者に支持されています。
「理屈ぬきで面白い!」と丸山誠司さん自身もコメントしており、現代の子どもに“働く忍者”という新しい発想を届ける意欲作です。「にんじゃラリーマン」は丸山誠司さんによる絵本で、会社で働く忍者のサラリーマン=「にんじゃラリーマン」たちが主人公です。彼らは「忍者になりたい」夢を叶える新商品「にんじゃくん!セット」を開発しますが、その商品が泥棒に盗まれてしまい、会社をあげて大捕り物に挑戦するドタバタストーリーです。テンポよく展開し、ユーモラスなお仕事コメディと忍者アクションが融合した新感覚の絵本です。
忍者絵本を選ぶ3つのポイント
1. 年齢に合った内容を選ぶ
0〜3歳なら繰り返しの多いシンプルなストーリー、4〜5歳なら冒険要素のある物語、6歳以上なら知識や謎解き要素のある作品がおすすめです。
ただし、これはあくまで目安。子どもの興味や発達段階は個人差が大きいので、「少し難しいかな?」と思う本でも、子どもが興味を示せばぜひ挑戦してみてください。
2. 遊びに広がる要素があるか
忍者絵本の最大の魅力は、読んだ後に「遊び」に発展すること。かくれんぼ、追いかけっこ、変身ごっこ——絵本から実際の遊びにつながる作品を選ぶと、親子の時間がより豊かになります。
マイステラの絵本も、「読んで終わり」ではなく、「読んだ後に何かが始まる」絵本を目指しています。子どもが主人公になる体験は、きっと次の遊びや冒険へのきっかけになるはずです。
3. 親も楽しめる内容かどうか
毎晩の読み聞かせ、正直に言えば疲れている時もありますよね。でも、親自身が「面白い!」と思える絵本なら、その時間が苦痛ではなく喜びに変わります。
ユーモアのあるもの、大人の知的好奇心を刺激するもの、心に響くメッセージがあるもの——親も一緒に楽しめる作品を選ぶことが、続けるコツです。
忍者ごっこ・絵本から広がる親子時間
絵本を読むだけでなく、その後の時間をどう過ごすか。それが、絵本の価値を何倍にも高めてくれます。
忍者ごっこで体を動かす
読んだ後は、ぜひ一緒に忍者になりきってみてください。手裏剣を投げる真似、壁を登る真似、煙の中に消える真似——子どもの想像力は無限です。
手作り忍者グッズに挑戦
折り紙で手裏剣を作ったり、新聞紙で刀を作ったり。MY STELLAでは印刷技術を活かしたパーソナライズ絵本を作っていますが、家庭でできる手作りの温かさも、かけがえのない価値があります。
「もし自分が忍者だったら?」と語り合う
「パパが忍者だったら、どんな術を使う?」そんな会話から、子どもの価値観や夢が見えてきます。忍者という題材は、親子の対話を自然に引き出してくれる魔法のツールです。」
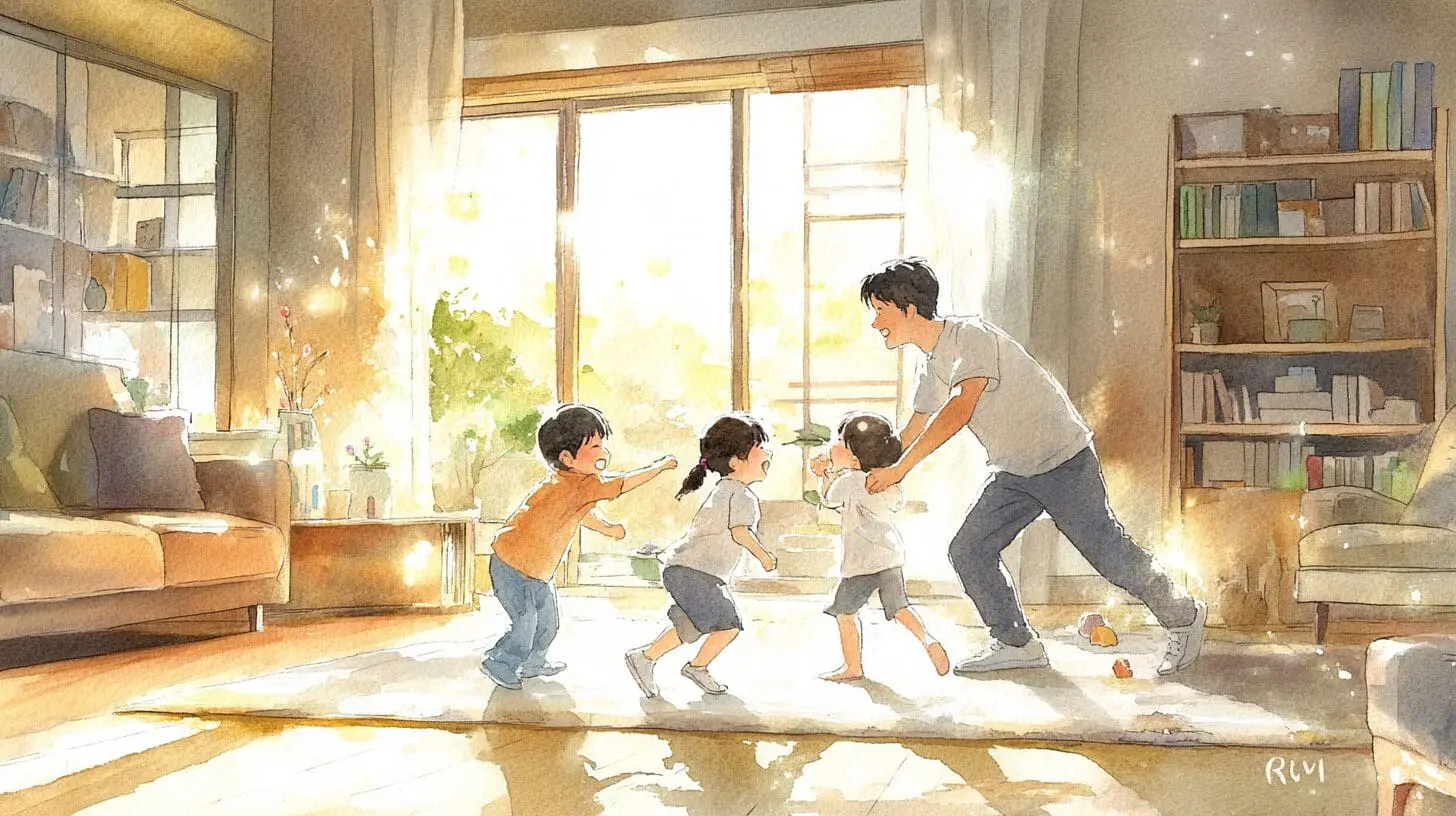
まとめ:一冊の絵本が、子どもの未来を変えるかもしれない
忍者絵本17冊、いかがでしたでしょうか。
私は印刷業に携わる中で、「残すこと」の価値を常に考えてきました。一枚の紙に込められた想い、一冊の本が生み出す体験——それは時に、人生を変えるほどの力を持っています。
息子が「忍者になりたい」と言った時、私は絵本を通じて、努力すること、協力すること、失敗を恐れないことの大切さを一緒に学びました。そして何より、親子で笑い合い、汗を流し、語り合う時間が、何にも代えがたい宝物になったのです。
MY STELLAで「子どもが主人公になる絵本」を作っているのも、同じ想いからです。一冊の本が、子どもの自己肯定感を育み、家族の絆を深め、未来への一歩を後押しする——そんな体験を、一人でも多くの家庭に届けたいと思っています。
あなたのご家庭にぴったりの忍者絵本が見つかりますように。そして、その一冊が親子の素敵な時間のきっかけになりますように。