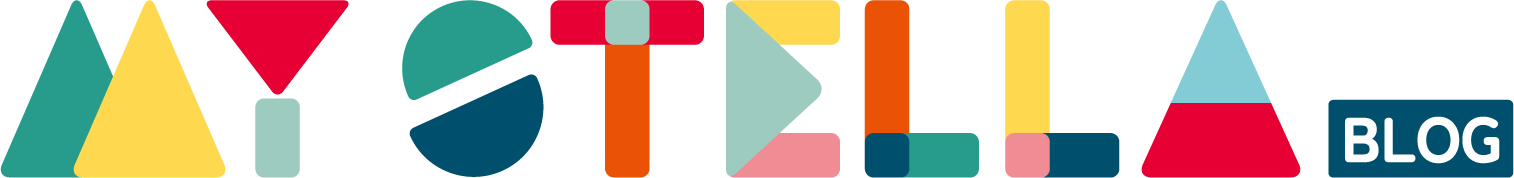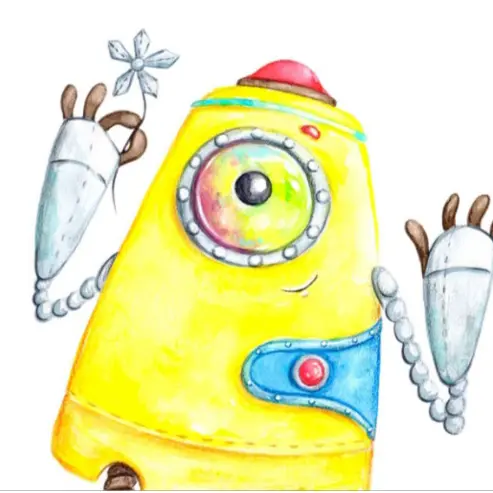「孫は目に入れても痛くない」ってことわざ、ありますよね。でも、実際に目に入れたら大変なことになるわけで…!(笑)祖父母の愛情って本当に尊いんですけど、時々「ちょっと待って〜!」って思うこと、ありませんか?
うちの実家に帰るたび、義母が「これも買ってあげる、あれも買ってあげる」って。幼稚園年中の娘は大喜びなんですけど、帰り道の車の中で「ママはケチ」発言が飛び出して、母の心はズタボロです…。でも、おばあちゃんの気持ちもわかるんですよね。かわいい孫には何でもしてあげたくなっちゃう。
今日は、5歳の娘を育てるエッグママが、祖父母世代の皆さんと一緒に考えたい「孫への愛情の伝え方」について、リアルな体験談を交えてお話しします。パパママ世代の方も、ぜひ参考にしてくださいね!
甘やかすことが孫をダメにする?子どもの成長に与える影響を気にしたい
「かわいい子には旅をさせよ」って昔の人は言ったけど、今の祖父母は「かわいい子には全部買い与えよ」状態(笑)。これ、短期的には子ども大喜びなんですけど、長期的にはちょっと心配なんですよね。
おばあちゃんの家に行くと、娘の目がキラキラ。「今日は何買ってもらえるかな〜」って顔してるんです。幼稚園で覚えてきた「おねだり技」も全開。「おばあちゃん大好き〜!」なんて甘えた声で言うもんだから、義母もメロメロです。
でも家に帰ってからが大変。「ママも買って!」「おばあちゃんは買ってくれたのに!」の連続攻撃。娘の中で「ママ=ケチ、おばあちゃん=優しい」の図式ができちゃってて、もうね、母の立場って…(涙)
「可愛さ余って憎さ百倍」じゃないけど、甘やかしすぎると我慢する力が育ちにくいんですよね。年長さんになる頃には小学校入学も見えてくるのに、このままで大丈夫かな…って本気で心配になります。
短期的ないい影響と長期的なストレスの実態を記事で紹介
先週、義実家でのこと。夕飯前なのに「アイス食べたい!」と娘が言い出して、私が「ご飯の後にしようね」って言ったら、義母が「まあまあ、今日は特別よ〜」ってアイス出しちゃった。
結果、夕飯はほぼ食べず。「ほら、だから言ったじゃん」って心の中で叫びつつ、顔では笑顔をキープ。この高度な演技、誰か褒めて…!
「三つ子の魂百まで」って言うけど、幼児期に身につけた習慣って本当に大事なんですよね。でも、それを祖父母に理解してもらうのが難しくて。だって皆さんの時代には「もったいない精神」で「残さず食べなさい!」が当たり前だったわけで、今の「無理強いしない育児」とは真逆なんです。
寝る時間も大きな問題。我が家は9時就寝を守ってるんですけど、おばあちゃんの家では「もう少し遊ぼ〜」で10時、11時…。翌日の幼稚園で眠そうにしてる娘を見ると、「私の育児、無駄なのかな」って落ち込んじゃいます。
日常シーンから見る甘やかしの実例とことわざの意味
スーパーでお菓子売り場を通るたび、「これ買って」攻撃。私は「今日はもう買わないよ」って言うんですけど、一緒にいる義母が「おばあちゃんが買ってあげる」の一言で決着。カートの中はお菓子だらけ。
娘も5歳になって知恵がついてきて、「ママがダメって言ったら、おばあちゃんにお願いすればいいんだ」って学習しちゃってるんですよね。これって、将来的に人間関係でも「ダメって言われたら別の人に頼めばいい」って考え方になりそうで怖いんです。
「雨降って地固まる」じゃないけど、こういう小さな衝突を繰り返しながら、お互いの距離感を探ってるんですよね。最初は「なんで私の言うこと聞いてくれないの!」ってイライラしてたけど、今は「まあ、たまにはいっか」って思えるようになりました。成長したな、私(笑)
距離感と役割分担の方法とその重要性を解説
親と祖父母の役割分担を気をつけて育てたい
「餅は餅屋」って言うように、子育てにも役割分担があるんです。親は日々のしつけ担当、祖父母は特別な思い出作り担当。これ、理想なんですけどね。
祖父母の皆さんにお願いしたいのは、「日常のルール」は親に任せて、「特別な体験」を提供する役割を担っていただくこと。例えば、普段はできない料理を一緒に作ったり、季節の行事を教えてあげたり。そういう「おばあちゃんの家でしかできないこと」が、孫にとって一番の宝物になるんです。
うちの義父は畑仕事が得意で、娘に野菜の育て方を教えてくれるんです。「このトマトは○○ちゃんが植えたやつだよ」って言われると、娘も嫌いなトマトを食べようとするんですよね。こういう体験は、私には提供できない貴重なものなんです。
距離感を守るためのコミュニケーション方法の記事
「お義母さん、あのですね…」って切り出すの、めちゃくちゃ勇気いりますよね。でも言わないとストレス溜まる一方。
祖父母の皆さんも、息子さん娘さんのお嫁さん・お婿さんから「ちょっとお話が…」って言われると、身構えちゃいますよね。でも、これって「孫のため」という共通の目的があるからこそ話せることなんです。
私が実践してるのは「サンドイッチ話法」。まず感謝→本題→また感謝、の順番で話すんです。
「いつも○○ちゃんをかわいがってくれてありがとうございます。実は今、食育に力を入れてて、おやつは週末だけにしたいんです。ご協力いただけると嬉しいです。いつも助けてもらって本当に感謝してます!」
こんな感じ。祖父母の皆さんも、直球で「お菓子買わないで!」って言われるより、こう言われた方が受け入れやすいですよね。

同居・近居のリアルな挑戦とことわざの教え
同居してる友達、めちゃくちゃ大変そう。「遠くの親戚より近くの他人」じゃないけど、近すぎるとお互いの生活が見えすぎちゃって、細かいことでイライラしちゃうんですって。
「子どもが泣いてるのに放っておくなんて!」って姑に言われたり、「そんなに神経質にならなくても」って呆れられたり。でもどっちも間違ってないんですよね。世代が違えば育児の常識も違う。
祖父母の皆さんが子育てされてた頃と今では、育児の情報も環境も大きく変わっています。「私たちの時はこうだった」という経験も大切ですが、「今はこういう考え方もある」という柔軟さも持っていただけると、親世代は本当に助かります。
この友達は「家庭内ルールシート」を作って、冷蔵庫に貼ってるそうです。「おやつは1日1回」「テレビは30分」とか、シンプルに。視覚化するとお互い守りやすいんですって。なるほど〜!
自己肯定感を育てる接し方を紹介
人として尊重する大切さを気にして育てたい
5歳にもなると、自分の意見をしっかり言えるようになってきます。幼稚園での出来事を熱心に話したり、「これがいい」「あれは嫌」ってはっきり主張したり。
祖父母の皆さんって時間に余裕があるから、じっくり孫と向き合えるんですよね。これは本当に羨ましい。うちの義母は娘の話をめちゃくちゃ聞いてくれるんです。「今日ね、幼稚園でね、お友達とね…」って延々続く5歳児トーク、私は正直途中で「うんうん」って適当に流しちゃうんですけど(ごめん娘)、義母は最後まで「それでそれで?」って聞いてくれる。
「雨降って地固まる」みたいに、子どもは話を聞いてもらえることで心が安定するんですよね。祖父母の皆さんには、ぜひこの「聞く時間」を大切にしていただきたいです。忙しい親にはなかなかできないことですから。

マイステラの絵本で大切な思いを育む工夫
そうそう、最近うちで大活躍してるのが「MY STELLA」のパーソナライズ絵本なんです!これ、娘が主人公になる絵本で、名前も見た目もカスタマイズできるんですよ。
義母にプレゼントしてもらったんですけど、娘が「これわたし!おばあちゃんありがとう!」って大喜びで。物じゃなくて、こういう「特別な体験」をプレゼントしてもらえると、親としても嬉しいんですよね。
絵本の中で冒険する娘を見ながら、「○○ちゃんは勇気があるね」「優しい子だね」って義母が声をかけてくれる。これ、すごく自己肯定感が育つと思うんです。物をもらう喜びより、こういう心の栄養の方が大事だなって実感しました。
祖父母の皆さん、孫へのプレゼントを考えるとき、おもちゃやお菓子の前に、こういう「心に残る贈り物」も選択肢に入れてみてください!

事例を交えた実践チェックリストを記事で紹介
やりがちなNG行動とは?ことわざで学ぶ育て方
「急がば回れ」じゃないけど、すぐに手を出しちゃうのもNG。娘が靴を履こうとしてるとき、義母が「時間かかるから」ってササッと履かせちゃうことがあって。気持ちはわかるんですけど、それだと成長のチャンスを奪っちゃうんですよね。
幼稚園の先生が言ってたんですけど、「できることは自分でやる」って習慣をつけるのが、この時期すごく大事なんですって。小学校に入る前に身につけておかないと、後から苦労するそうです。
あと、親の前で親を批判するのは絶対ダメ!「ママは心配性ね〜」とか、軽い気持ちで言ってるんでしょうけど、子どもは「ママはダメな人」って思っちゃいます。実際、幼稚園の先生に「最近『ママはダメ』って言うことがありますね」って指摘されて、ハッとしました。
祖父母の皆さん、孫の前では息子さん娘さんの味方でいてください。それが、孫の心の安定につながるんです。
祖父母がやって欲しいOK行動の解説
逆にこれは嬉しい!っていう行動もたくさんあります。
時間をプレゼントしてくれること。物より思い出!公園で一緒に遊んだり、絵本読んでくれたり。幼稚園児って体力があるから、親は正直ヘトヘトなんですよ。そこを祖父母の皆さんが「公園行こうか!」って連れ出してくれると、めちゃくちゃ助かります。
それから「ママとパパが決めたことだから守ろうね」って言ってくれること。これ言われると、めちゃくちゃ嬉しい。味方がいる!って思えるんです。
実際の家庭シーンから学ぶ事例
友達のBちゃんは「お泊まり約束カード」作ったんですって。寝る時間とかテレビの時間を絵で描いたカード。これを祖父母の家に貼っておくと、子ども自身が「約束の時間だよ」って言えるようになるらしい。天才か!
5歳くらいになると、ルールを理解して守ろうとする力も育ってきます。「おばあちゃんの家でも守る約束」って形にすると、子どもも納得しやすいんですよね。
私も真似して作ってみようかな。娘もお絵描き好きだし、一緒に作ったら守ってくれるかも。
祖父母の存在が孫に与えるポジティブな影響を記事で解説
愛情と安心感の積み重ね
「情けは人のためならず」。祖父母の無条件の愛情って、巡り巡って子どもの心を豊かにするんですよね。
娘が幼稚園で嫌なことがあった日、義母に電話したら「○○ちゃん、おばあちゃんのところおいで〜」って。その日は義実家に直行して、たくさん甘えさせてもらいました。翌日、娘は何事もなかったかのように元気に登園。
親だけじゃなくて、祖父母っていう「第三の居場所」があることで、子どもの心は安定するんだなって実感しました。これ、本当にありがたいことです。
祖父母の皆さん、あなたの存在が孫にとってどれだけ大きな支えになっているか、自信を持ってくださいね!
成長を支える祖父母の役割を気にして育てたい
義父が戦争の話をしてくれたとき、娘は「こわいね」って言いながらも真剣に聞いてました。5歳にもなると、こういう大切な話も理解できるようになってくるんですよね。
「温故知新」。古いことを知って新しいことを学ぶ。祖父母は生きた歴史の教科書。親世代では教えられない、昔の遊びや暮らし、戦争の記憶。そういう話を聞けるのって、本当に貴重な体験なんです。
祖父母の皆さん、ぜひご自身の経験や思い出を、孫に語り継いでください。それが、孫の心の財産になります。

親と祖父母が共に育む子どもの未来
協力関係の築き方
「一人では限界、みんなでやれば無限大」…なんてことわざはないけど(笑)、子育てはチームプレイなんですよね。
私は月1で義実家で「家族ミーティング」もどきをしてます。といっても、お茶飲みながら娘の様子を報告するだけ。でもこれ、すごく効果的!祖父母も孫の成長を知れるし、私たちの考えも伝えられる。
特に義母が「なるほど、今の育児はそうなのね」って理解を示してくれると、めちゃくちゃ嬉しい。完全に同意してもらえなくても、「そういう考えもあるのね」って受け止めてもらえるだけで救われます。
祖父母の皆さん、息子さん娘さんの話、聞いてあげてくださいね。「私たちの時は違った」じゃなくて、「今はそうなんだね」って受け止めることから始めてみてください。
子どもの幸せな未来を目指して
結局、親も祖父母もみんな「子どもの幸せ」を願ってるんですよね。方法が違うだけで、ゴールは同じ。
「百聞は一見に如かず」。理屈で説明するより、一緒に育児してみるとお互いの大変さがわかるんです。義母に娘を1日預けた日、迎えに行ったら義母がヘトヘトで(笑)。「今の子育ては大変ね〜」って労ってくれて、それ以来、無理なお願いが減りました。
祖父母の皆さんも、たまには孫と丸一日過ごしてみてください。そうすると、親世代の大変さも理解できるし、孫との特別な時間も持てて一石二鳥です!
まとめ:気をつけて育てたい、ことわざと共に学ぶ孫育て
「孫は目に入れても痛くない」けど、目に入れたら大変(2回目)。祖父母の愛情は本当に尊くて、ありがたくて。でも、その愛情の伝え方をちょっと工夫するだけで、子どもはもっと健やかに育ちます。
物より時間、命令より共感、批判より協力。この3つを意識すれば、きっとうまくいく!
「育児は育自」。子どもを育てながら、私たち親も、祖父母の皆さんも、みんな一緒に成長していくんですよね。完璧じゃなくていい。ちょっとずつ、一歩ずつ。
祖父母の皆さん、どうか息子さん娘さんの子育てを温かく見守り、時には手を貸し、時には見守ってあげてください。あなたの愛情が、孫の未来を照らす光になりますから。
今日も夕飯前のアイス問題と格闘中の私でした。明日は義実家でおやつルール、もう一回説明してみようかな…。頑張れ、私!(そして全国の祖父母の皆さん、パパママの皆さん!)