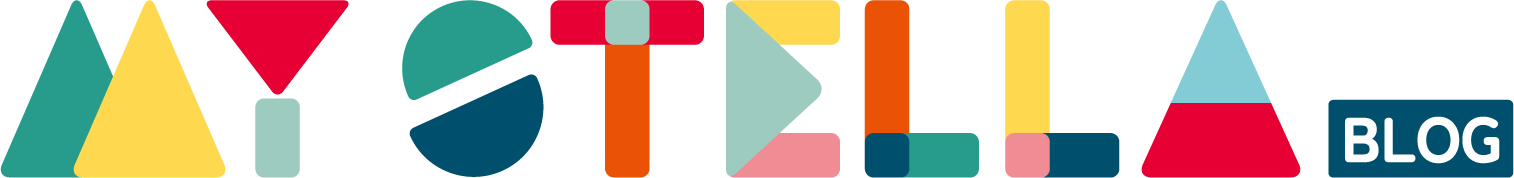こんにちは! MY STELLA(マイステラ)のニコです。前回、子どもの創造力を育むキュビスムについてご紹介したところ、「そもそもキュビスムって何?」という声をたくさんいただきました。今回は、このユニークな芸術について、もう少し詳しくお話ししていきますね!✨
キュビスムはこうして生まれた! 🎨
『20世紀の美術』(E.H.ゴンブリッチ)によると、キュビスムは1907年、パリで誕生しました。当時27歳だったピカソは、従来の「一つの視点から見た絵」という常識を覆す、まったく新しい表現方法を生み出したのです。
「キュビスムとは、対象を同時に複数の視点から見た姿として表現する手法であり、20世紀初頭の美術に革命的な変化をもたらした」(『20世紀の美術』ゴンブリッチ)
なぜ「キュビスム」って呼ばれるの? 🤔

『ピカソ 芸術は危険である』(クルーゾ)によると、「キュビスム(Cubism)」という名前は、フランスの美術評論家が使った「キューブ(立方体)」という言葉から生まれました。物を様々な角度から見た形が、まるで立方体を組み合わせたように見えたからなんです!
例えば、りんご一つでも…
- 上から見ると→お花みたい! 🌸
- 横から見ると→しずく形! 💧
- 斜めから見ると→卵みたい! 🥚
子どもの見方とキュビスムの不思議な関係 👀

児童画の研究者でもある鬼丸吉弘氏曰く、興味深い発見が報告されています:
「4-6歳児の視覚認知の特徴として、単一の視点にとらわれない多視点的な観察能力が挙げられる」
つまり、子どもたちは自然と「キュビスム的な見方」をしているんです!例えば…
- お母さんの顔を正面から描きながら、横顔の鼻も一緒に描く ✏️
- お家の中の様子を、屋根を取っ払って上から見たように描く 🏠
- 大好きなぬいぐるみの前と後ろを同時に描く 🧸
キュビスムの特徴を見てみよう 🖼️

キュビスムの面白いところは、「正解」がないこと。『美術教育概論』では、以下のような特徴が挙げられています:
- いろんな角度からの視点 🔄
- 上から見た形
- 横から見た形
- 中が透けて見える形 全部を一つの絵の中に表現できちゃいます!
- 自由な色使い 🎨
- 空が紫色でもOK
- りんごが青色でもOK
- 好きな色で表現できます
- 形の変化を楽しむ ✨
- 四角いものを丸く
- 丸いものを三角に
- 自由な形に変身させられます

キュビスムで育つ子どもの感性 💫
さらには、キュビスムを通じて育つ力について、こんな指摘がされています:
- 観察力 👀
- じっくり見る習慣が身につく
- 新しい発見ができるように
- 想像力 🧠
- 「もしかして…」が広がる
- 自由な発想が育つ
- 表現力 🎨
- 自分らしい表し方を見つける
- 伝えたいことを形にできる

まとめ:子どもとキュビスムの素敵な関係 🌟
東京都美術館の教育プログラム資料では:
「子どもたちの自由な視点は、時として大人の固定観念を超える創造性を持っている」
と言われています。
キュビスムは、そんな子どもたちの素直な感性と驚くほど相性がいいんです。特別な道具も技術もいりません。大切なのは、子どもと一緒に「へぇ~!」「すごい!」「面白い!」を共有する時間。その積み重ねが、子どもの創造力を育てる最高の栄養になるんです 🌱
さぁ、明日から始めてみましょう! あなたとお子さんの「楽しい!」が、新しい才能の芽を育てていきます 💖
#子育て #アート教育 #キュビスム #創造力 #子どもの感性 #創造性教育 #育児を楽しむ
参考文献・引用元
書籍:
- 『美術の物語』E.H.ゴンブリッチ著(フィービー・スノウ訳)(ファイドン株式会社, 2019年)
- 『ピカソ作品集』大高保二郎著(東京美術, 2022年)
- 『児童画のロゴス―身体性と視覚』(勁草書房、1981年)
- 『幼児の造形表現』花篤實・岡田憼吾 編著(保育出版社、2003年)